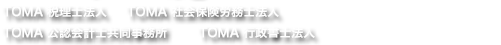自筆証書遺言の保管制度とは
昨今、相続対策でお悩みの方が大変多くなっております。
その対策として、様々な方法がございますが、一つ挙げるとすれば、それは遺言がございます。
遺言書は大きく分けて2種類あり、1つは自筆証書遺言、もう1つは公正証書遺言として定められています。
自筆証書遺言は、本人自身による作成・保管、また相続開始後は相続人が家庭裁判所に対し確認(検認)を求める手続きが
必要とされる遺言です。一方、公正証書遺言は、公証人の下、2名以上の証人が立ち会い作成される遺言であり、公証人
による遺言の有効性の確認、遺言内容に対する助言が必要とされており、財産価値に応じた手数料が発生します。
ここでは、主に「自筆証書遺言」についてお話させて頂きます。
2020年7月に施行された遺言書の保管制度に関わる遺言書は自筆証書遺言です。
自筆証書遺言保管制度とは、遺言書の原本を法務局(遺言保管所)が保管する制度です。
自筆証書遺言は、手続きに伴う手間がかからず、手軽に作成可能であり自由度が高い点が特徴です。
一方、遺言書の紛失や不当な改ざん行われるリスクがあり、被相続人の意向を伝える上での確実性や遺言の正当性の問題が
指摘されていました。
自筆証書遺言保管制度は、このような自筆証書遺言のメリットである自由度を担保しつつ、自筆証書遺言に存在するリスク
を軽減することを目的として創設された制度です。
自筆証書遺言保管制度を利用する際、はじめに行う作業は、遺言書の作成と遺言保管所の選定です。
自筆遺言書を作成する場合、決められたフォーマットに従って作成しなければ、無効になってしまう場合があります。
また、どの遺言保管所を利用するかは遺言者の住所や本籍地に応じて予め定められていますので、
要件を確認し該当する遺言保管所に申請を行いましょう。
なお、遺言書の撤回や内容の変更が必要な場合も、遺言保管所への届出が必要です。
撤回の届出は、遺言書の原本が保管されている遺言保管所に対して直接行わなければなりません。
この記事では、遺言書の保管制度の簡単な概要についてご説明させて頂きました。
他にも、遺言者が亡くなった後の遺言保管事実証明書等、様々な手続がございます。
より詳しい情報をお知りになりたい方は、法務・税務面からの検討に加え間違いの無い判断をするため、
専門家にご相談頂くことをお勧め致します。
ぜひ、藤間司法書士法人にお気軽にお問合せくださいませ。







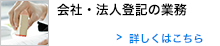
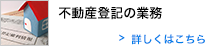
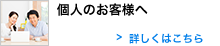


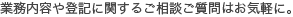




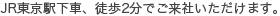



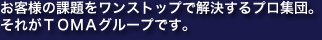
![TOMAコンサルタンツグループ株式会社(東京/シンガポール[アジア統括]/ ロサンゼルス[アメリカ統括])](../common/images/f_text_09-2.png)