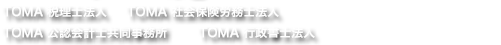年の瀬
12月に入り今年も残すところあと僅かとなりましたが、この時期になるとよく「年の瀬」という言葉を耳にします。
年の瀬とは、「年末」「年の暮れ」という意味で、「その年が終わりを迎えようとしている時期」、「師走の慌ただしい時期」また「年の暮れが訪れ世間一般が忙しい時期」のことだそうです。明確には決まっていませんが、全国的に12月13日頃から正月準備に入ることから、中旬以降を指す場合が多いようです。
年の瀬の「瀬」は、「川の中の歩いて渡れる程度に浅い所」のことで、「川の中の急な流れ」の意味もあります。通常、浅くて流れが急な場所である「川の瀬」を渡るには船ですら困難であると言われ、ましてや歩いて渡るとなると「命がけ」になるので、急いで渡ろうとして慌ただしい行軍となります。
この「瀬」の前に「年」が付いたのが「年の瀬」で、1年の中でも一番忙しくバタバタする時期のことを意味するようになりました。
しかし、なぜ「年の瀬」は忙しくて慌ただしいのでしょうか?それは、江戸時代の商いの習慣にありました。
江戸時代の庶民は商品を「ツケ」で買い、代金の清算は盆と暮れにしていました。
特に暮れは、正月に向けて何かとお金が必要な時期で、借金を返済したら餅を買うなどの正月の準備が出来なくなる人がいたほどです。精神的にも苦労がかさみ、まさに川の瀬に立った、危機的な状況と言えたでしょう。「年が越せた」というように無事に借金を返して正月を迎えられることが、庶民のささやかな喜びでした。
一方、「年の瀬」は商人にとってはツケを回収する稼ぎ時でした。商人は除夜の鐘が鳴るまでにツケを回収しようと走り回り、お金が集まったら徹夜で帳簿をつけていたそうです。
このように、「年の瀬」は、江戸時代の商人や庶民にとって、正月を無事に迎えられるかの差し迫った時期なのです。つまり、ドタバタした様子が、川の瀬を渡るイメージにつながり、「年の瀬」の語源になりました。
皆さんもこの時期はお忙しいかと思いますが、年内に登記申請しなければならないものや、年明けの登記申請に向けて今年中に確認しておきたいことなどがごいましたら、お気軽に藤間司法書士法人までお問い合わせください。







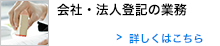
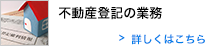
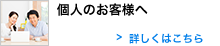


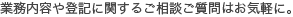




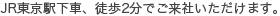



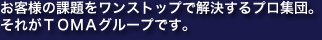
![TOMAコンサルタンツグループ株式会社(東京/シンガポール[アジア統括]/ ロサンゼルス[アメリカ統括])](../common/images/f_text_09-2.png)