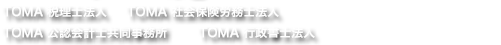遺言のその先へ。遺留分の放棄で想いがつながる相続を
「うちは遺言をきちんと用意しているから大丈夫」。
そう思っていても、相続の現場では思わぬ行き違いが起こることがあります。
その理由のひとつが「遺留分」という法律上最低限保障されている遺産の取り分。
たとえ遺言で「全財産を妻に」と記しても、子どもが遺留分を主張すれば、遺言どおりにはいかないことがあるのです。
つまり、遺言だけでは安心しきれないのが、相続の現実。
特に、不動産や自社株など分けにくい資産があるご家庭では、相続開始後に思わぬトラブルになることも少なくありません。
そこで検討したいのが「遺留分放棄」。
あらかじめ家庭裁判所の許可を得て、「自分の遺留分は主張しない」と合意する制度です。例えば、「自宅は妻に」、「会社の株式は後継者に」・・・。そんな想いを実現するために、他のご家族には生前贈与などで感謝を伝える。相続人全員が納得のうえで合意をしておけば、将来の紛争防止に有効です。
一方で、よく混同されるのが「相続放棄」。
こちらは相続が始まってから期限内に家庭裁判所に申述する手続きです。相続人としての立場そのものを放棄するものです。つまり、財産も負債も一切受け取らない代わりに、最初から相続人ではなかったことになります。
それに対して、「遺留分放棄」は生前に行うもので、相続人の立場はそのままに、遺留分だけを主張しない手続き。遺産の一部を受け取ることもあれば、債務を引き継ぐこともあります。似ているようで、意味も効果もまったく異なる手続きです。もちろん、無理な遺留分放棄は認められません。家庭裁判所は、放棄の合理性・自由意思・代償の有無を慎重に判断します。
遺留分の放棄は、ご家族の想いを調和させ、未来を穏やかにつなぐための選択肢ともいえます。藤間司法書士法人をはじめとするTOMAコンサルタンツグループでは想いを法のかたちに整え、家族の安心を未来へつなぐお手伝いもしています。遺言や相続でお悩みの際には、ぜひお気軽にご相談ください。







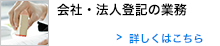
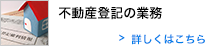
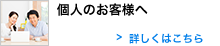


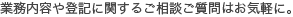




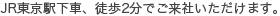



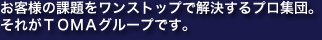
![TOMAコンサルタンツグループ株式会社(東京/シンガポール[アジア統括]/ ロサンゼルス[アメリカ統括])](../common/images/f_text_09-2.png)